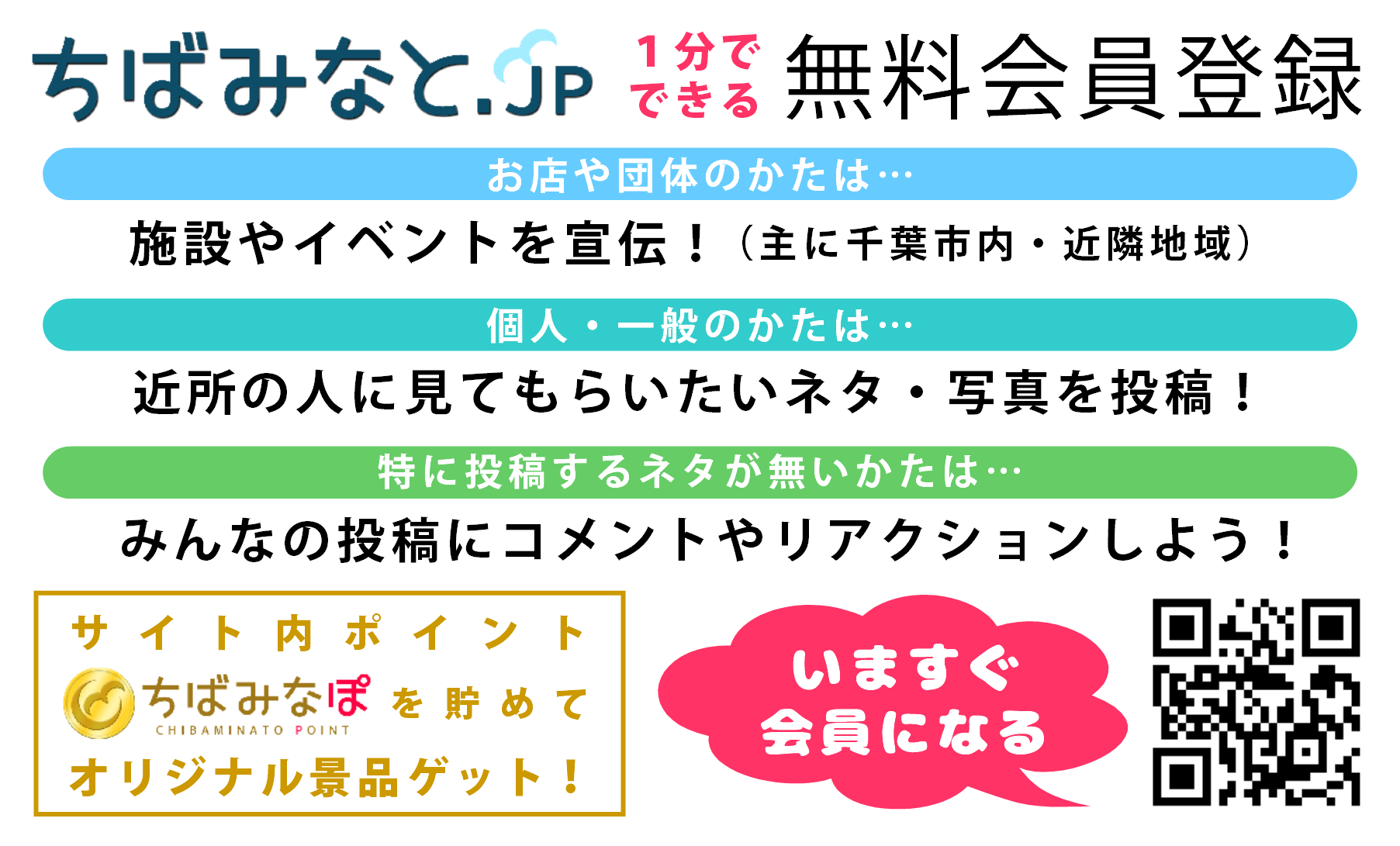♯第4話 まっしぐら娘と暮らせば Wouldn't It Be Loverly?
1635
2022/3/16
以下は 2 年前に書かれた内容です
1
早春の休日の朝、目が覚めたアキラは辺りを見回した。
知らないベッド、見知らぬ部屋。
うららかな千葉港が見える窓の下には、自分のスーツケースが一個置かれていた。
あぁ、そっか。記憶が蘇ってくる。ここは学生時代の恩師、千神雄造先生の部屋だ。昨日その娘のナコの一人住まいの家に引っ越したのだった。
「保護者としてここに住む」と大家の前で宣言した。ナコの秘密を知って記憶を消されかけた翌日に。なんであんなこと言ったのか。アキラは自分が信じられなかった。
コンコンとノックの音、続いてドアが開いた。カモメの仏頂面が現れた。
「朝メシ。できたってよ」
アルはそう告げるとフンと鼻を鳴らして消えた。
居間に行くと、ダイニングのテーブルに目玉焼きとご飯が並んでいた。目玉焼きの端っこがちょっと焦げていた。
「アキラさん、おはようございます。お待たせしました」
小さなキッチンからエプロン姿のナコが、みそ汁の椀を手に出てきた。
「なにこれ」
「朝ごはんです。どうぞ」ナコはにっこり言った。
「いらない。俺、朝食わないから。コーヒーだけちょうだい」
アキラが手を振ると、ナコはちょっと涙目になった。テーブルでポテトをつついていたアルがアキラをにらんだ。
「おい。ナコが一生懸命作ったのにそんな言い方ないだろ。せめて一口くらい食えよ」
「朝から食えない体質だからしょーがないの。じゃ、一口だけ」
面倒くせえ、とアキラは席に着き、箸で焦げた目玉焼きをつついた。
食後、すべて食べられた空のお皿を、アルは不機嫌そうに片づけていった。
「アキラさん、洗濯回すので、洗い物ください」ナコが洗面所から顔を出した。
「すげー、二層式じゃん!」シャツを持っていったアキラは年代物の二層式洗濯機に目を見張った。「昔、田舎のばあちゃんちで見たことある。いいの。俺のも入れて」
「わけたほうがいいですか?」
「まあ、そっちが気になんないなら別にいいけどさ」
「ああっ」アキラのシャツの襟を見たナコが驚きの声をあげた。
「え?」
「これ…ふだん洗っていますか?」襟の汗じみを前に、ナコは目を皿のように開いた。
「そりゃ、洗わんわけないっしょ」
「どのくらい」
「どのくらいって…休みにちゃんと。月、週に一ぺんほど」
ナコはシャツを鼻に持っていき、吸い込むと眉をひそめた。と、突如アキラのスーツケースに走った。そして開ける。押し込んであった服や下着が全部飛び出した。
「なにすんだよ勝手に」
「全部洗います!」ナコは全部のアキラの服を抱えると洗面所に駆け、消えた。
やがて小さなベランダにナコの制服ブラウスやアキラのトランクスがはためいた。
ソファで寝っ転がってアキラがスマホをいじっていると、ナコが箱を持ってきた。白い包みを取り出し、丁寧に開けると、赤い衣装の雛人形が現れた。
アキラの視線に「おひな様です」とナコが言った。
「ああ、へえ」女の春の節句とやらのやつか。初めて見た、とアキラは思う。
「小さい頃、お母さんが買ってくれたんです。このお人形のお顔、ナコに似てるからって。そう見えます?」
「見えますかもね。敬語はよしてよ」
『そろそろ泊まりに来てよ』『ライブの後な』と女とメッセージのやり取りをしながらアキラは言った。アルがそれをしらーっと見ていた。
そのとき。ズンと地面が揺れた。
「地震だ」アルが言い、ナコと目を見合わせた。
スマホの画面に出た地震情報を見ると、×の地点は北緯35.6度、東経140.1度を示していた。
「ここだ。震源地、千葉みなとだと」
ナコは緊張した面持ちで父の革手帳を取り、開いた。
リングに付いた赤い石が発光していた。
「どこへいくんだよ」
「震源地に、です」
ポートタワーがそびえ立つ家族連れやカップルでにぎわう港の桟橋を、ナコはどんどん進んでいく。アキラは追い、アルも飛んでついてきた。
ナコは港の立ち入り禁止エリアの柵の前で止まった。そして無人の波止場を指した。
「…あそこに何か、いるんです」
ナコの手のなかでリングの石は赤く光っていた。
「何か?」
「そして、地震も起きる」ナコは低く言った。「私がこの石を使うと、おかしなものもたくさん現れる」
アキラは大晦日の晩の出来事を思い出した。
「モノレールで、黒い影みたいのが俺たちを襲った。あれは一体なんなんだ?」
ナコは首を振った。
「わかりません。これをお父さんから渡された後から現れ始めて。あの辺から」
ナコは波止場に目を移すと、柵を越えようと足を掛けた。
「よせよ」その襟を猫の子の首を掴むようにアキラはつかんだ。
「一緒に住む限り、物騒はごめんだ。戻るぞ」
アキラは桟橋に踵を返した。ナコは慌てて、追う。
柵の向こうの波止場の地面に、♯の文字がふうっと浮かんで、消えた。
2
数日後。アキラは昼時に仕事場の製鉄所から歩いて数分の波止場に停まる、キッチンカーに足を運んだ。港を臨む桟橋広場の一角に、白を基調としたクラシカルなシボレー・グラマンのsilver spoonが現れた。学生時代からベーシストとしてアキラと相方を組む銀嶺の営む移動店舗だ。
「春の種まきをするには、ぴったりの陽気だね」
中古バンを改造した車内のキッチンで、片耳イヤホンをした銀嶺はカメラをセットしながらアキラに振り向いた。
「なにしてんの」アキラは車内を覗く。
「レシピ動画始めようと思って」銀嶺は言った。「で、引っ越しは?」
「済んだ。あとひとつ大事なの以外」
「どう。彼女との新生活は」
「サイアク」席に着くと、顔を突っ伏す。
「あの娘…見かけはしおらしいけど、実は頑固者で意地っぱりで、思い込んだらまっしぐらでさ。飯もしっかり作っちゃって毎日食わされて調子狂う。ヘンなカモメもガーガーうるさいし」
「箱の中の猫をついに拾ったか」銀嶺は、ホットサンドを作りながらいつもの無表情で言う。「デズがうらやましがってたぞ。ナコちゃんと二人暮らしなんて最高、いいなって」
「保護者代わりなのに。親父さんが帰るまでの一時的だよ。仕方なくの」
「自分から望んだ。よっぽどあの子のこと」
「そういうんじゃなくて。ただ…あいつの目、忘れられなくてさ」
ナコと初めて会った夜。『サニーが憂鬱』の演奏とともに現れたナコは見知らぬ路地に迷い込んだ子猫のようにおびえながら、必死にこちらを見上げていた。その瞳は曇り空のような憂いの灰色だった。何か抗えない罠に囚われ、重たい運命を背負ってしまった諦観、それでも独りで闘おうとする、リアル・ブルーというか。
銀嶺は言う。「お父さんがいなくなって、困り果てていたんだろう。まだ14なのに可哀そうに」
「そんなタマじゃない!」アキラはテーブルを叩いた。その後、桜吹雪のなかナコに襲いかかられたのだ。「望みがかなう」という、父親から渡された怪しげな赤い石のリングで鎧の戦士に豹変する娘に。あのとき一瞬脳全体が発火したように感じた。なぜか記憶は消えなかったが。しかし、銀嶺にこんなこと言えるはずもない。
「やっちまった。こんな面倒なことに関わるなんてどうかしてた。後悔してる」
ぶつぶつ言っていると視線に気づいた。銀嶺の瞳、アキラが『女の子のおメメ』と呼んでいる、まつ毛の長い鳶色の目がすうっととこちらの目を見入った。
「…なんだよ」
「刺激的な新生活を、楽しんでるようだ」
「なんでそうなるの」アキラは再びテーブルを叩いた。
「やっぱ同居は撤回する! 大体俺がひとと一緒に暮らせるわけなかった」
ずっと一人暮らし、もっというと十歳のときからほぼ一人できたのだ。人から縛り付けられるきゅうくつだけは絶対の願い下げだ。銀嶺は頷いた。
「出ていくなら、早いほうがいい。彼女が傷つかないうちに」
「そうするわ。決めた」
そのとき。ズンと地面が振動した。車内の皿やカップがカタカタと音を立てた。
「またここが震源地かな」
銀嶺はグラスを抑えて言った。アキラは柵の向こうに広がる無人の波止場を見た。
3
夜になった。みなとハウスのナコの家の時計は十時を回った。
「遅いな。あいつ」帰宅しないアキラにアルは口ばしをとがらした。
「うん」ナコはおひな様を静かに眺めて言った。アルはほとんどない肩をすくめた。
「えらそうなこと言って、あいつビビって逃げたか。このまま帰って来なかったら…」
アルが横目でナコを見ると、ナコは微笑んだ。
「だとしても無理ないよ。アキラさんは悪くない。やだよね普通。こんな無気味な状況」
「ナコ」
「私は、平気」
アルはフフンと鼻を鳴らした。
「まあ…こうなることは最初から予想ついていたよ。あいつ生意気だし気に食わなかったんだ」そしてナコに片目をつぶった。「大丈夫、オレがついてるからさ! ナコ、こんどの休みさ、ふたりでポートタワーの屋台のロングポテト、食べにいこう」
「いいね!」ナコはにっこり頷いた。
時刻はさらに進み、アルはナイトキャップをかぶって専用ベッドでスヤスヤ眠ってしまった。アキラは帰らない。ナコは父の手帳を開いた。「真仲央」という父の走り書きが出た。
雄造の消息もわからず、途方に暮れていた時に見つけたこの名前。この人が何か知っているかもしれない。名前の字を何度も何度も見て、どんな人だろうと想像した。探した。駅前のジャズバーで演奏するジェリーフィッシュというジャズバンドで、その名を発見した。そして勇気を振り絞って店まで会いに行った。
アキラは9つ年上で、父のいた大学を出た後は蘇我の製鉄会社に勤務していて、月に一、二度ここでピアノを弾いていた。初めて見たアキラは、ピアノの前で目をつぶり、空間に何かを描くように鍵盤に指を這わしていた。ナコが挨拶すると、前髪の間から切れ長の瞳でしばらく見下ろし、やがて氷が溶けるように端正な顔を緩ませた。ぽっと心に光が灯り、冷えた身体がじんわりと温まった。初めての感覚だった。ここに住むと言ってくれたときは胸が熱くなった。でも、元の独りきりに戻った。望み通りに。ナコは目を閉じる。
と、地面が揺れた。父の革手帳を開く。リングが赤く光っている。ナコは立った。
なぜこの孤独な戦いが目の前にあるのか。呪われた運命なのか。突き止めるだけだ。
4
立ち入り禁止区域の高い柵を昇り、またいで越える。そして、手帳を地面に置いた。
と、わずかに地面が動き、何かが蠢き叫ぶような声が聞こえた。
「だれ?」ナコは叫んだ。
「答えて、だれなの?」
そのとき。
潮風に乗って、ストリングスを弓で掻き弾いたような低い声が響いた。
『…シャープ』
はっとナコは辺りを見回した。暗がりには何も見えない。
と、ナコの足元のコンクリートの地面にみるみる、何かが浮き出てきた。
♯
シャープ…?
ナコは地面のふしぎな文字に見入った。と、その文字のなかから黒い影がタールのように涌き出た。そして黒い触手をナコに伸ばしてきた。
出た。やつらだ。後ずさりし、ナコは逃げる。幾本もの触手が追ってきた。
地面に置かれたリングを取ろうとするが、足を掴まれて激しく転んだ。触手が足首、手首にからまり、ついに地面に倒されて動けなくなった。やがて首にも絡まりついていく。身体じゅうを縛り付けられながら、ナコは痛みと怖さで悲鳴にならない声をあげた。
そのとき。エンジンの轟音が響いた。
黒バイクがスモークの向こう現れ、停まった。ヘッドライトが地面に仰向けに拘束されたナコの身体を照らした。
バイクはスロットルを上げ、発進してナコに向かってきた。ナコは観念して目をつぶった。
そのタイヤは、ナコに取り付く影を断ち切った。影が悲鳴をあげる。黒い触手が手や足から離れ、ナコは赤石リングに手を伸ばし指につけた。一瞬で、鎧の戦士と化した。
ナコは容赦なく影たちを引きちぎり、鎧のブーツで踏みつけ、見下ろした。
「失せろ。巣に帰りな」
断末魔の悲鳴をあげて黒影は港の暗い波間へと去っていった。
ナコはもうもうとたつ白煙のなか、黒バイクに振りかぶり、対峙した。
ライダーはヘルメットを取る。
「物騒はごめんて言ったろ」
アキラの顔が港湾のライトに照らされた。
ナコの目の怒りはすうっと治まり、その姿はもとにもどっていった。
「…もう帰らない、のかと」
「預けてたこいつを取りに行ってた。引っ越しの荷物」アキラはバイクのDUCATIの字に手を置く。
「じゃあ」
「保護者に無断で、夜中に勝手に出歩くな」
ナコはポロポロと涙をこぼし頷いた。波止場の向こう、東京湾対岸の灯りがチラチラと揺れていた。
地面にあった♯の模様は、ゆっくりと消えていった。
5
数日後の夜。クリッパーには、『ひなまつりライブ JerryFish』の看板が出ていた。
「ナコちゃん。こういうことは僕に聞いちゃだめだよ」
ライブ前、カウンター席で勉強をしているナコに、黒ベレー帽のマスターが連立方程式が書かれたノートを返した。
「昔っから金勘定と数字の計算はからきしでね。理系のアキラくんに聞いて」
デズはアキラの後を、巨体のコバンザメのように引っ付いて歩いていた。
「いいなーいいなーナコちゃんみたいな子と一つ屋根の下で暮らすなんて。どんなスウィートなかんじなの? おしえて」
アキラはデズを叩きのめした。「阿呆。こっちはいろいろ命がけなんだよ!」
デズは巨体を返すと今度はナコに行き、手を合わせた。
「9歳も上のデリカシーのないひねくれ者のオッサンと暮らすのウザいだろうけど、がまんしてね」
傍らでアルはぼやいた。「またナコと水いらずの暮らしになると思ったのにな」
ふてくされるアルに、険しくデズは釘をさした。「おいカモメ!妙なことにならないようにきっちり監視しとけよ」
「じゃポテト3皿よこしな」
和装スレンダーなドレスに身を包んだ新一郎が、アキラに寄ってきた。
「いい子だな。頭のネジが一本抜けてるおまえに一応言っとく」そしてアキラのつむじの逆毛を抑えてその耳に囁いた。
「手を出すなよ」
「阿呆くさ。めちゃガキじゃん」舌を出し、ビールのグラスを傾ける。
「うん。だから、少なくともあと4年は待て」
むせるアキラに客の女が近寄ってきた。「ねえアキラ。このあと来るよねうち」
「悪い。期末テスト近いんだ」
「期末テスト…?」
「量子物理学者の娘のクセに、数学が壊滅的」
そう言い、アキラがピアノに向かうと、刺すような視線を感じた。ダブルベースを抱えた銀嶺が、アキラをじっと見ていた。その目に言う。
「何も言うな。ギン」
夜も深まったみなとハウスでは、ミュージカルの歌声が流れた。
ソファでアキラが白黒の洋画をスマホに映し、数学のノートを持ったナコがそれを覗いた。
「あ、この可愛い曲、さっきライブでやりましたよね」
「『Wouldn't It Be Loverly』ね」アキラは言った。1964年のミュージカル映画 「マイフェアレディ」の挿入歌だ。ロンドンの下町の路上、寒い3月の夜。オードリー・ヘプバーン演じる貧しい花売り娘のイライザが、憧れの暮らしを妄想して歌う。
All I want is a room somewhere,
Far away from the cold night air
あたしの一番の願いはね
石炭くべた暖炉のあるあったかい部屋で
チョコレートをたらふく食べて過ごすんだ
ああ、それってなんて素敵なの
で、大きな椅子に座ったまんま一歩も動かない
春がやってくるまでね
ああ、そうだったら、いいのにな
で、あたしの膝には、彼氏が頭をもたげている
温かく私を大切にしてくれる人さ
ああ、もしそうなったら、いいのにな
すっごく、すごく素敵じゃない?
アキラの右肩が重くなる。見ると同居人の娘が寄りかかり、こくっこくっ、と居眠りしていた。目の前で涼しげに微笑むおひな様と目が合った。
「…なにやってんだかね?俺」
語りかけ、ふと眠るナコの顔を見て目を丸くした。
「ほんとだ、そっくり」
こうして、早春の夜は静かに更けていった。
二人を監視して息をひそめる、シャープと名を告げた、何かとともに。
Wouldn't It Be Loverly
つづく
以上は 2 年前に書かれた内容です
このまとめ記事の作者
ログインしてコメントしよう!